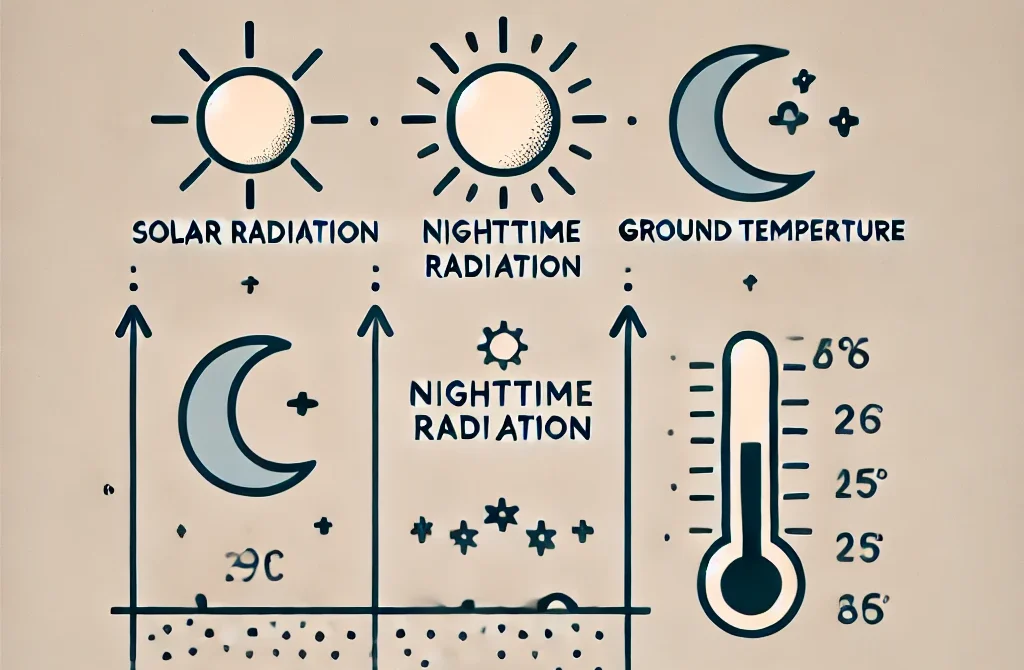1. 日射量と気温の関係
日射量とは、太陽から地表に届くエネルギーの量を指します。単位はW/m²(ワット毎平方メートル)で表され、気温に大きな影響を与えます。そして、気温は1年を通して室内環境に大きく影響します。
- 日射量が多いほど気温は上昇
日中、特に晴天時には日射量が多くなり、地表が加熱されることで気温が上昇します。 - 季節による変化
夏は日射量が多く気温が高く、冬は日射量が少なく気温が低くなります。夏至の頃(6月20日から22日頃)は、太陽光度が高く、建物が日射を受ける時間も長くなるため、全天積算日射量が最大になります。 - 地表の特性による違い
アスファルトやコンクリートは熱を吸収しやすく、都市部の気温を高くします(ヒートアイランド現象)。日射を受けた地面は蓄熱するため、熱容量の関係で、月平均気温は8月頃が最高となります。
2. 夜間放射と気温の関係
夜間放射とは、昼間に太陽熱で温められた地表面から大気に向かって放出される地表面放射(地面→大気)と、大気中の水蒸気が地表に向かって放出される長波長の大気放射(大気→地面)の差のことです。
- 夜間放射が強いと気温が下がる。
晴天時は放射冷却が強く、気温が大きく下がりやすいです。また、建物の表面温度も低くなりやすいです。 - 雲があると放射冷却が抑えられる
雲があると、地表からの放射熱が再び地表に戻され、気温の低下が緩やかになります。 - 地面の種類による影響
草地や水面は放射冷却が強く、夜間の気温低下が大きくなります。
3. 地中温度の特徴
地中温度とは、地面の中の温度のことで、地表の気温よりも安定しています。
- 深くなるほど温度変化が小さい
地表近く(50cm程度)の温度は季節の影響を受けますが、1m以上の深さでは年間を通して安定した温度を保ちます。 - 夏は涼しく冬は暖かい
地中は外気よりも温度変化が小さいため、地下室などは夏に涼しく、冬に暖かくなります。 - 地熱利用の活用
空調設備に地中の温度を利用することで、エネルギーの消費を抑えることができます。
4. デグリーデーとは?
デグリーデー(Degree Days)は、暖房や冷房の必要性を示す指標で、建築やエネルギー管理に用いられます。
- 暖房デグリーデー(HDD, Heating Degree Days)
日平均気温が10℃以下の日を暖房期間として、期間内の日平均気温と基準気温(14℃)との差を積分したもので、暖房に要する熱量を見積もるための指数として用いられます。寒冷地ほど値は大きくなります。 - 冷房デグリーデー(CDD, Cooling Degree Days)
日平均気温が24℃以上の日を冷房期間として、期間内の日平均気温と基準気温(24℃)との差を積分したもので、冷房に要する熱量を見積もるための指数として用いられます。温暖地ほど値は大きくなります。 - エネルギー消費の予測に活用
HDDやCDDを使うことで、建物の年間の暖房・冷房エネルギーの目安・必要度を計算できます。
まとめ
- 日射量が増えると気温は上昇し、夜間放射が強いと気温が下がる。
- 地中温度は外気温よりも安定しており、建築の温熱環境に活用できる。
- デグリーデーは暖房・冷房の必要性を示す指標で、エネルギー管理に役立つ。
これらの知識を活かして、より快適な建築設計やエネルギー管理を行いましょう!